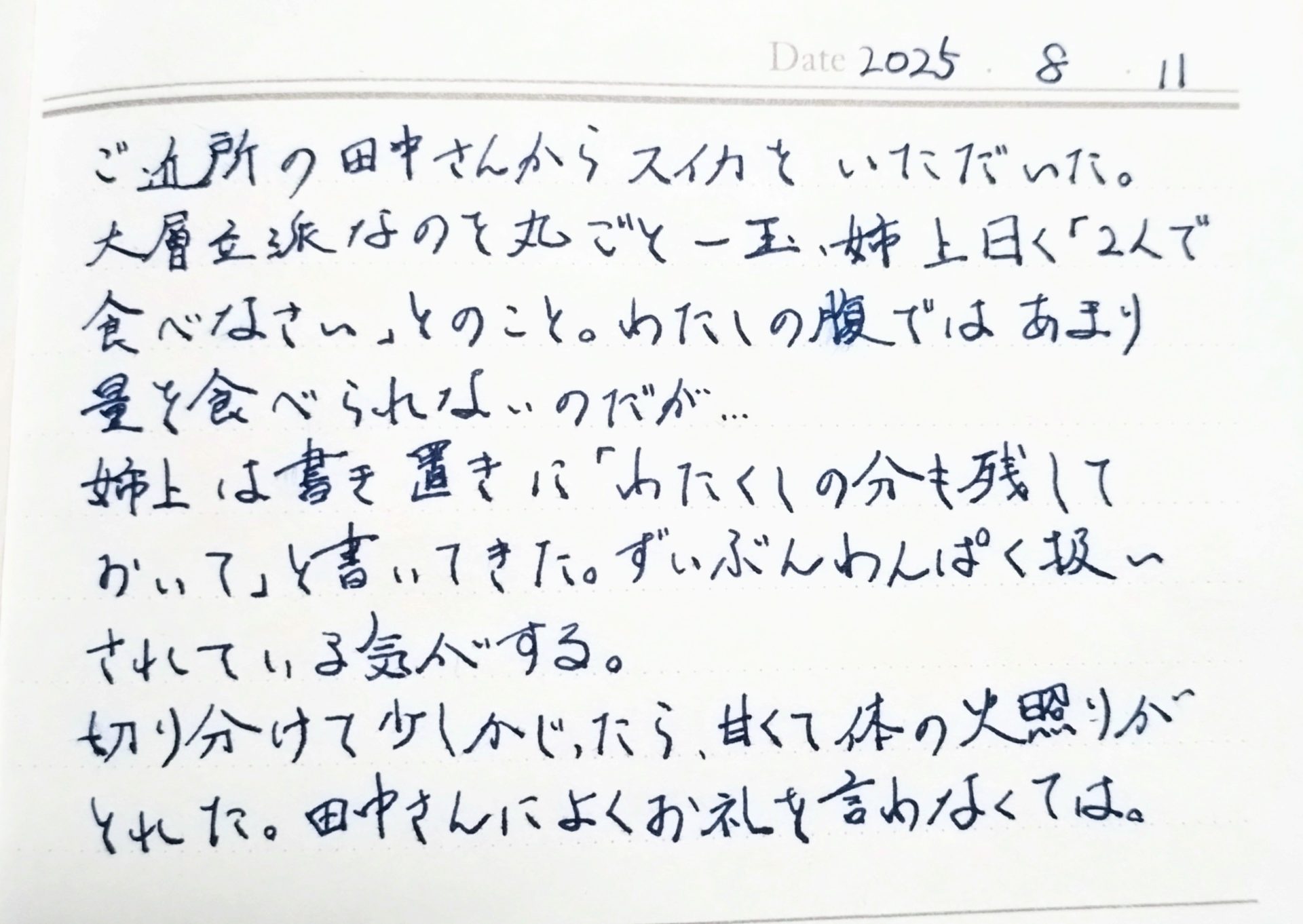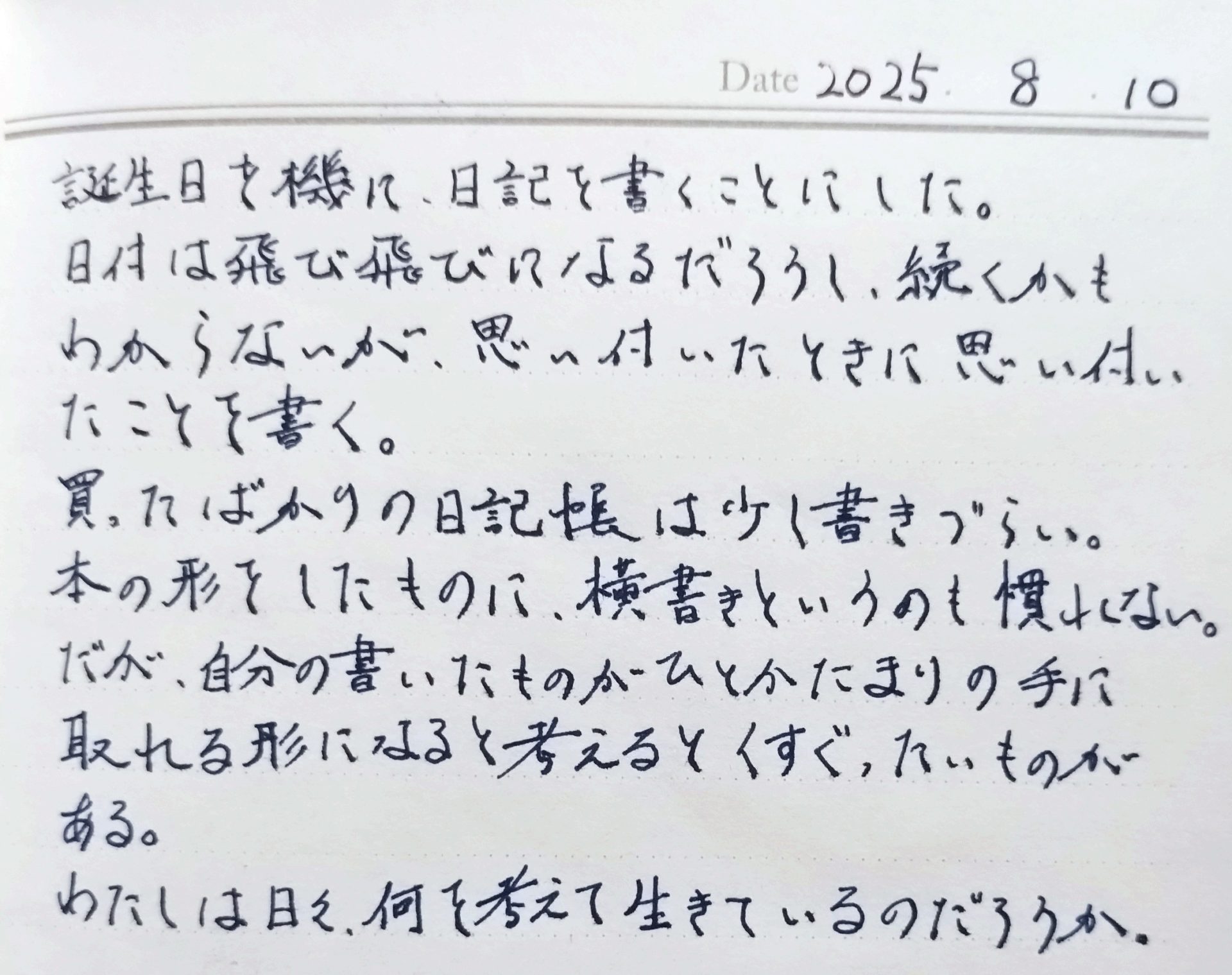障子越し、淡い春の日差しが差し込む部屋で、一人の青年が静かに正座している。やや日焼けしているもののイグサの香りを残した畳の上には、白地に青の釉薬がつややかな陶器の器に水が張られていた。青年は手に持ったハサミで花の茎を切り、花器に据えられた剣山へ花を生けていく。次の花を手に取り、ふと鼻先をかすめた香りに自分が呼吸を忘れていたことを思い出すと、一つ大きく息をついて、すっかり乾燥して上下ではりついた唇を舌で湿す。
器にはスプレー咲きの小さな花が翼を広げるように枝を伸ばして生けられており、これから生けられるであろう大輪の主役を待ちわびているようだった。青年は、手に持った花をじっと見つめ、ほころんでいるつぼみのガクを指先で撫でる。いまだ咲ききらないその花は、紅白まだらの入った花弁が固いガクを押しのけていた。
明日の昼にはすっかり開くだろう花とにらみ合うようにして、青年はぴたりと動きを止める。
そうして、動かなくなってどれだけの時間が経っただろうか。
「露青(ろせい)、お昼ごはんができましたわよ」
若い女の声が部屋に響く。障子が開かれ、縁側から直接差し込んだ日の光に照らされた青年――露青は、それでも微動だにしなかった。髪に咲く薄青の朝顔も、花を持つ手も、着物の袖一つさえ揺れない。
彼が花の世界に没入しているのを見て取った、こちらも髪に青い朝顔を咲かせた着物姿の女――青海(あおみ)は、小さくため息をついて部屋に入り込むと、露青の隣に座して花器に生けられた花々をしばし眺めた。どうやら、主役となる花を据えることさえできれば、この作品は完成するようだ。
「ほどほどになさいまし。お昼はとっておきますわよ」
聞こえているのか、いないのか。露青はやはり身じろぎ一つせず、花とにらみ合っている。青海は「でしょうね」とばかりに腰を上げ、静かに部屋から出て行った。
とっぷりと日が暮れ、昼に声をかけてから一度も露青を見かけなかった青海は、改めて露青の部屋へ向かった。花を生け始めると寝食を忘れることは、露青にはままあることではある。しかし、青海は決してそれを是としているわけではない。集中しているところを邪魔するのは本意ではないため、食事の一度までなら見逃すが……元来体の弱い露青を栄養不足や睡眠不足で放っておけば、いつなにが起きるかもわかったものではないのだ。
冷蔵庫に残ったままの昼食はさておき、そろそろ仕上がる夕飯は食卓に引きずり出してでも食べさせる、と息巻いて露青の部屋に来た青海は、障子に部屋の明かりが映っていないのを見て眉をひそめた。
「休む気になったのかしら」
眠っているのであれば、急に起こして驚かせるのもよくない、と青海はそっと障子を開ける。夜空には星明りしかないが、室内はそれよりもずっと暗かった。障子を開けてもはっきりとは見通せない室内に、青海はきゅっと口を結んで壁へ手を伸ばす。
明かりをつけると、そこには見事に完成された生け花の花器と、切り捨てた茎や枝葉に突っ伏すように倒れた露青の姿があった。
「露青!」
駆け寄った青海が抱き起しても、露青は起きる気配がない。ぐったりと畳に放り出された手は冷え切っており、まるで死人のような顔色をしている。
青海は恐る恐る露青の鼻先に手をかざし、それでようやく呼吸を確認して、大きく安堵の息を吐いた。
「だから、ほどほどになさいと言ったでしょうに……」
頭痛をこらえるような顔をして、青海は露青を畳の上にあおむけで寝かせた。顔に張り付いていた葉をとりのけて、生けられた花を部屋の隅へ一時避難させると、紙の上に乗せられていた茎や枝葉をまとめる。それから押入れを開けて布団を敷くと、「せめて布団で寝なさい」と露青を揺すり起そうとするが、彼は一向に起きそうになかった。仕方なく彼の着物の帯を解き、襦袢姿にすると、半ば引きずり、半ば転がすようにして布団へ納める。
「手のかかる弟だこと」
言いながらも慣れた様子で掛布団を整え、枕の位置を合わせてやり、青海は部屋の明かりを落とした。食事は起きてからでもどうにかなるだろう、と考えて、先ほどまとめた捨てる枝葉を持つと、部屋を後にする。
露青は、翌朝になっても起きることはなかった。
***
淡く光る、花の海。
目を開けた露青は、無音の世界でただほのかに光を放ちながら揺れる花々を見上げて、その香気を胸に吸い込んだ。身を起こせば、あたり一面に多種多様な花が咲き乱れている。菊の真隣りに向日葵、薔薇に桜草、百合、牡丹、躑躅、木瓜、椿、鬼灯、露草。季節も植生も問わず無節操に咲く花のすべてが、盛りをきわめて一番美しい花姿を誇っていた。傷んだり萎れたりしているものは一輪たりとも存在しない。
月も星もない夜空は、日の出まで二時間ほどと思しき薄明かりの色に濃淡がついている。
「ここは……」
水を飲むことも忘れていたせいで、かすれた声が落ちる。よほど広大な場所なのか、音が反響して戻ってくることもなく、露青の声は目の細かい砂のように崩れて消えてしまうようだった。
ぐるりと周囲を見回しても、あるのは花ばかりで、人工物や人間はおろか、生き物がいるような気配もない。
「……わたしは、とうとうあの世へ来てしまったのか」
どうやら地獄のようには見えないが、とあごに手を当ててしばらく考え込んだ露青は、膝に手をついて立ち上がることにした。
普段よりも格段に軽い体に、やはり肉体を置いてきてしまったようだ、と妙に冷静に考えながら、露青は足元の花をよけて地を踏み、ゆっくりと歩きだす。とげのある花々も彼の素足を傷つけることはなく、着物の裾に寄り添うように揺れて、光の粒を散らした。
「華道狂いが見る夢のような場所だな。……こうも季節を無視して咲かれると、いささか無粋なようにも思えるが」
数分、するすると歩を進めても景色に変化はない。ただ、足裏に当たるひんやりとした土の感触だけが露青に現実感を与えていた。
「この花は、手折って生けることはできるのだろうか」
身一つで歩いていて、花器も鋏もない露青は、足元に咲いていた水仙に足を止めた。花の機嫌をうかがうようにそっと撫で、できるだけ茎を傷ませずに折り取れるところを探っていると、ふと一歩先に金属質な光が見える。彼が不思議に思って草をかき分けた先には、いつか家の蔵で眠っているのを見た花鋏があった。
「……なぜ、ここに? 確かに家にあったものだが、蔵にあったものはかなり錆びていたはず」
濡れたような艶を帯びて、花の光をまとった花鋏へ、露青は導かれるように手を伸ばす。すんなりと手の中に納まった鋏をまじまじと眺め、重さを確かめ、その刃を開いて閉じて……と空を切った。刃の鳴る音はしなかったが、滑らかに動く感触に露青は一つうなずく。
「なぜここにあるのかは知らんが、あるのなら使ってもいいのだろう。……生けたとて、それを見る者がいるとも限らんが」
見渡す限りの花の海を前に、露青はじわじわとこみあげてくる笑みを隠さなかった。一度は無粋と評したものの、やはり現実では容易に成しえないような花の組み合わせを、思いつく限り試すことができるのだ。露青にとってはまさに夢のような機会であり、見る者はなくとも、この状況に心が浮き立つのも無理はない話だった。
水仙、竜胆、節分草。薊、紫陽花、金鳳花。菖蒲(あやめ)に菫、金盞花。
色とりどり、どれも月下に照らされているかの如く淡く光る花々は、あまりに容易に露青の手の中に納まった。不思議なことに、いくらか花を切って開けた土の上には、様々な色や形をした花器も現れる。
まるで「使ってくれ」とばかりに手元に集まる生け花の道具は、どれも丁寧に扱われて磨かれてきた物の年季と誇りをまとっているようだ。
「わたしに、都合がよすぎやしないか?」
ひとりごちながらも、露青は着々と集めた花と花器を選り分けていく。夜目にもまぶしく輝く白い陶磁器の花瓶に同じく白い水仙を、灰皿めいた重厚な黒い平皿には金に輝く黄花節分草を。透明で大きなガラスの平皿には紫陽花の大きな花の塊を囲うように小手毬をもこもこと置き、かと思えば吊り花瓶に凌霄花を生けて、吊る場所を探して松の枝にかけたり。計画もなにもあったものではなく、ただ見て合うと思った組み合わせを置いてはのけて、露青はひたすらに花を生け続けた。
***
床の間に置いた花はすっかり開き切って、甘やかな香りを部屋に満たしていた。
露青を寝かせた布団の傍らで、青海は静かに考え込んでいる。
「もう、丸一日……」
倒れていた露青を布団に収めてから、彼は一度も目を覚ましていない。
朝食の時間になって、起きてこない露青に朝の光を直撃させても、昼の時間に布団を引きはがして半身を起こさせても、彼は身じろぎどころか表情の一つも変えずに眠り続けているのだ。顔色があまり優れないのはいつものことではあるが、生気のない様相で寝息の音もなく静かに横たわるさまは、青海にとってあまり見ていたいものではなかった。幼少期から病がちだった露青は、幾度か生死の縁をさまよったことがある。その時と、今の彼はよく似ているのだ。
家事をこなし、華道教室の生徒たちを教え、忙しく日常を回しながら、青海は度々露青の部屋を訪れては、彼の息と脈を確かめて胸をなでおろしていた。朝、昼と、露青が起きてくるものと考えて作った前日の食事を温め直して自分の胃に収めるたび、青海はかすかにため息をつく。夕刻に呼んだ医者は、「過労で眠っているだけでしょう」と言い、翌日になっても意識が戻らないようなら点滴の用意をしてまた来る、と帰っていったところだ。
「いい加減に、起きたらいかがですの」
医者に診せて着乱れた襦袢を直し、布団をかけてやりながら、青海はぽつりとつぶやいた。
露青は、やはりなにも応えず、眠り続けるばかり。
***
露青はもくもくと花を生け続けていた。彼の足元にあった花、目についた花は順繰りに刈り取られ、ほかの花と引き立てあうように美しく生けられる。その度に、「次はこれを使え」とばかりに新たな花器が現れた。露青は公園でドングリを集める少年のように、周りを見ているようで花と花器しか見ていないまま、花の海をさまよう。
花が刈り取られたところは、露青がしばらく目を離すとまた別の花で埋められていた。彼には自分がどちらから来たものかも判然としない。目印もない大海原に揺れる小船のように、ゆっくりと流されて移動を続けるばかりだ。
洋の東西を問わず、およそ現代に存在する花で、なおかつ園芸品種であればなおのこと、露青は多くの花を見てきたはずだった。その彼の目から見て、この花の海には大きな違和感がふたつある。
一つは、実物はおろか写真やスケッチですら見たことがないような花が存在すること。
そしてもう一つ。
「これだけ花があって、朝顔だけが見当たらない」
花の海を構成するのは、露青に馴染みの深い、観賞用として愛でられる園芸品種の花々が主だ。だというのに、日本における園芸品種改良の代表と言っても過言ではないだろう「朝顔」だけがなかった。
「桜も、菊もある。露草や時計草もあるのだから、一日花ゆえということはないだろう。……」
露青は顎に手を当てて考え込み、それからしばらくして、自身の左側頭部へそっと手をやった。常日頃からそこに咲く、自身の象徴ともいえる花の感触。薄青い朝顔が、指先に触れる。
「……わたしか、あるいはわたし達が、朝顔だから……だろうか」
ことここに至り、露青はやっと姉のことを思い出した。もはや尊崇の域で青海を慕い、自身の拠り所としてきた露青にしてみれば、ありえないことである。いくら花に目が眩んだとはいえ、「あの世に来たのか」と思いながら、片割れを失ってひどく憔悴しているだろう青海の心配一つ、頭に浮かばなかったとは。
露青はようやく、獲物を狩るような眼で花々を見るのをやめ、深々と呼吸をした。
「……帰らなくては。姉上のもとへ」
ここが本当に「あの世」であるにしても、露青に姉のことを忘れさせるような場所であるならば、自分がいるべき場所ではない、と彼は判断した。
「神か仏か知らないが、祖霊信仰の者を家から引き離そうとは、勝手なことをしてくれるものだ」
聞くものが聞けば――どころか姉にも叱られそうなとんでもない悪態をついて、露青は手に持ったままの鋏を見やる。これはもともと、彼の家の蔵にあったもの。手に入れた場所も、最初に露青が目覚めた場所のすぐ近くだ。同じ場所から来たもので、きっと先祖に仕えた道具。この鋏を頼みにすれば、いつかは家へ、姉のもとへ帰れるはずだと目算を付けた。
「迷い子の鉄則は、その場から動かないことだが……よもやこんな場所まで、姉上(当主)に迎えを頼むわけにもいくまい。どうか、わたしを助けてはくれまいか」
露青は鋏を捧げ持つようにして語り掛け、静かに目を閉じる。やがて再び目を開くと、花鋏は月もないのにつやりと光って、数歩先に咲いた芙蓉の花を映した。そっと近寄れば、幹の根元にはやはり花器が静かにたたずんでいる。
「生け続ければ、戻れるのだろうか」
露青は花器を手元に引き寄せ、それから芙蓉の花を枝から切り取り、その場に座った。
「弓もないのだ。わたしにできることは、生けることくらいだろう」
***
露青が目覚めなくなって、一日半が経過している。
彼が起きたときにすぐ水や食事の用意ができるよう、青海は自室から露青の部屋へ布団を持ち込み、彼の隣で浅く眠った。しかし、日の出の時間になってもやはり目覚めない露青に、彼女の顔はかすかに青ざめて生気を失っている。
「……相変わらず、寝相のよろしいこと。一度起きてまた眠ってしまった、というわけでもありませんわね」
口ぶりばかりは冷静に、しかしかすかに震える手で自分の布団をたたむ。
――このまま露青が、二度と目覚めなかったら?
考えたくもないようなことが脳裏をよぎって、青海は小さく唇を嚙んだ。かろうじてそれを言葉に出すことはせず、浅くなりかけた呼吸を静かに整える。
「わたくしが、落ち着かないでどうしますの。お昼を過ぎたらお医者様をお呼びしますのよ」
自分が万全でなくては、看病などできはしない。自身にそう言い聞かせて、青海は昨晩用意しておいた着物に着替え、身支度をする。きっちりと帯を締めてしまえば、どうにか体の芯を保てそうに思えた。
腹が減ってはなんとやら、と朝食の支度をしに台所へ行こうとして、いまだに呼吸音すら乏しく眠り続ける露青を見下ろす。まぶたはおろか、まつ毛の先すら動かず、ともすれば精巧な人形にすら見えるほど冷たく整った寝姿に、青海は息を詰めて膝をついた。
「ねえ、……ねえ、露青、……起きてくださいまし、露青」
そっと触れた頬は、血の気が引いて青海の手のひらよりも随分と冷たい。それがひどく恐ろしくて、青海は声を震わせ、露青を呼び続けた。額にかかった前髪をよけ、彼の髪に咲く朝顔の花に触れる。
「帰ってきたくないほど、幸せな夢を見ているの? ……お願いだから、わたくしひとり、置いていかないで……」
今にも力尽きそうに俯いた彼女の瞳から、ぽつり。露青の朝顔へ、涙が一つ、落ちてはじけた。
***
露青は、いくらか冷静に周囲を観察しながら、変わらず花を生け続けていた。一つ生けては歩を進め、一つ生けては花をかき分け、そうして新たに気付いたことがある。
花器は、一度に一つしか見つからない。花器を追うことで、道が分岐するということはないようだった。
「道標、なのか」
振り返っても、花を刈られて露出した地面は、新たな花の波に呑まれてかき消されている。しかし立ち上がって目を凝らせば、淡く光る花の海には、わずかに輝くかたまりがいくつも見えた。彼が花を生けては置いてきた花器が、灯をともしたようにぽつりぽつりと露青の足跡を示しているのだ。
ひとつ前の花器へ戻ろうとすれば、花の海の輝きに呑まれて灯を見失う。諦めて一番新しい花器へ戻ってみれば、再び見えるようになった花器の軌跡は緩やかに弧を描いていた。
そうして花の海をさまよって、どれほどの時間が経ったのか。空の様子も変わらなければ、空腹や喉の渇き、疲労もないため、露青にはどれだけここで過ごしたかが分からなかった。しかし、十ではきかない数の花器に花を生け続けて、相当の時間が経っていることは間違いない。
帰るにしても、いつになるやら……とつきかけたため息が、すっと引っ込む。
次の花器を探して顔を上げた露青の目に、最初に生けた水仙の花瓶が飛び込んできたのだ。
「戻って、来たのか」
水仙は生けられる前よりもはっきりと輝きを増し、白く光っている。そして、その光に照らされるようにして、花瓶に絡みつく蔓が露青の目を引いた。
「朝顔……」
朝顔の花には、この場所に咲く花々が放つ白くかそけき光は宿っていない。そのせいか、まるで光を吸い込むように周囲からは沈んで見えていた。
気づけば、露青はゆっくりと足を進めて、朝顔の前に膝をついていた。導かれるように手を伸ばし、海の色をした青い花弁が宿す露に指先で触れる。
その瞬間、この世界で初めて、露青の耳に自分以外の声が響いた。
――お願いだから、わたくしひとり、置いていかないで……。
ひどく遠く、そして久しぶりに聞こえた姉の声に、露青はぐっと熱くなった胸を押さえて深呼吸をする。青海の声は静かだったが、同時に頼りなく震えていて、自分がどれほど心配をかけたのかが突きつけられているようだった。
「……姉上、あねうえ。すぐにそちらへ戻るから、もう一度、わたしを呼んでくれ……」
きゅうと喉が詰まる感覚がして、露青の頬を涙が伝う。それは朝顔の花に滴って、ぽつりとはじけた。
***
眠っていた露青の目元に、すう、と一筋、涙が伝った。
「露青? ……露青!」
わずかに眉根を寄せた露青に、青海が必死で呼びかける。眠ってしまってから二日近く、表情一つ変えることのなかった露青の変化に、青海は起こすなら今しかないのではと彼の肩をゆすった。
「ん、う……」
眩しさをこらえるようにまぶたに力が入り、露青はまつ毛を震わせた。かすれた声でうめいて、うっすらと目を開く。
「あ、ねうえ。少し、痛い……」
着たままの襦袢にしわを寄せるように、きつく掴まれた肩の痛みが、露青をはっきりと覚醒させた。
「起きましたのね……!?」
聞いているのかいないのか、青海は露青の肩を掴んだまま、新たに涙をあふれさせる。ぽた、ぱたぱた、と寝具へ降り注いだ雨の音を追うように、彼女は露青のかたわらへ崩れ落ちて顔を覆った。
「ああ、もう……!」
ずっと同じ姿勢で眠っていた体が軋むのを、半ば無理矢理動かして、露青は青海のほうへ寝返りを打つ。寝返り一つで「はぁ」と息をついて、それから露青は静かに肩を震わせて泣く青海の背へ手を伸ばした。
「姉上が呼んでくれたおかげで、帰ってくることができた」
ありがとう、と告げれば、青海は泣き顔に怒りをにじませて体を起こす。
「……ごめんなさいは?」
「こういう時はありがとうだと、以前……」
「……」
「申し訳なかった」
「よろしい」
布団から身を起こした露青は、そのままふらりと立ち上がると、朝日が降り注ぐ縁側へと向かい、目をすがめた。庭へ降りようと外履きをつっかけようとしたところで、青海に後ろから腕を掴まれる。
「どこへ行きますの、起きたばかりで」
「蔵へ」
「後になさい」
不満げに見返す露青の視線をものともせずに、青海は彼を部屋の中へ引き戻し、たたんであった彼の着物を広げた。
「誰もいないとはいえ、そんな薄着で朝から外に出るなんて。それに、二日も飲まず食わずで寝ていましたのよ? また倒れたら大変じゃありませんの」
つらつらと真っ当なことを並べられて、露青には反論のしようもない。ほら、と広げられた着物に袖を通して、もそもそと着付けを始めれば、青海は満足げにうなずいて部屋を出ていく。
「急に食べたらお腹を壊すでしょうから、お吸い物を用意しますわ。朝食が済んだら、一緒に蔵に行きましょう」
花の形をした麩が浮いた吸い物をゆっくりと飲んで、露青はようやく、体の実在を確かめたような気がした。食道、胃、と吸い物の熱が広がって、自分の体の輪郭が朝の冷たい空気から分離していく。向かいで味噌汁と卵焼き、白飯の朝食を口に運ぶ青海は、一口吸い物を飲むごとに顔の血色がよくなっていく露青を見て柔らかくまなじりを下げた。
「随分久しぶりのような気がしますわ」
「二日も経っているというのが信じられないのだが……わたしが生けた花は、もうだいぶしっかりと咲いていたな」
「あなたが眠っているうちに咲き切りましたのよ」
食事を終え、食器を片付けると、二人で庭に出る。朝露の名残でつっかけのつま先を濡らしながら、整えられた庭を歩いて横切ると、庭の中でも隅のほうに、露青の目指す蔵があった。日当たりのよくないその一角に、静かに重々しく佇立する蔵は、姉弟どちらにとってもあまり馴染みのない場所だった。
「もう一つの蔵はよく使いますけど、こちらにはなかなか来ませんわね」
「お爺様が虫干しをしているのを見たきりだったはずだ。普段使うものは仕舞われていない……」
母屋から持ってきた鍵で蔵の戸を開け放ち、風を通す。案の定、埃とカビの匂いが流れ出てきた。蔵の中にこもっていた空気が入れ替わるまで、少し二人で外を歩く。
「どうしてここに?」
「眠っている間に、花鋏を見たんだ。それに見覚えがあった」
「……ここに、仕舞われていたものですの?」
「ああ。だが、ここで見たときとは様子が違う」
戸口から覗き込んで、蔵の中の空気が少しマシになっているのを確認すると、露青はそっと薄暗がりの中へ足を踏み入れた。木製の重厚な棚には、さほど多くの品物が仕舞われているわけではない。寸法も様々の桐箱がまばらに置かれているばかりだ。
露青に続いて蔵に入った青海は、彼の後を歩きながらあたりを見回す。露青のお目当ては花鋏だというので、比較的小さな箱を探してきょろきょろとしていた。
「……おそらく、これだろう」
蔵の中でも特に奥まった一角、棚の一番下の段で、露青はしゃがみ込んで小さな桐箱を取り上げる。筆で書かれた異体字は、どうにか「はさみ」と読めるようだった。露青は箱のふたをずらし、ちらと中を確認するとうなずく。
「戻ろう」
「閉じてしまいますの?」
「これを、蔵に戻す気があまりしなくてな」
鋏の箱を持ったまま、二人は蔵を出て、戸に施錠した。
露青の部屋へ戻り、改めて箱を開けると、そこには古びた絹布の上ですっかり錆びきった花鋏が眠っている。そっと手に取って、閉じた刃を開こうとした露青は、小さくため息をつくと首を横に振った。
「錆を落としても、もう使うことはできないだろう」
「でしょうね……」
茶色くざらついた錆に覆われて、微動だにしない鋏は、なにも言わない。
「……やはり、あれは死者の記憶の世界だったのだな」
花鋏を手にしたまま、露青がつぶやく。それを聞きとがめた青海は、キッと眉根を寄せた。
「どういうことですの」
露青は静かに顔を上げると、姉と視線を合わせて、とつとつと語る。
「眠っている間……わたしは、華道狂いの見る夢のような場所にいたんだ」
それは普通に露青が見た夢ではないのか、と青海は口を挟みかけたが、緩やかに語る露青に気圧されて、口を閉ざした。
「四季を問わず、植生も問わず、花という花がほのかに光って咲き乱れていた。どの花も一点の傷もなく、萎れているものもない。すべてが花の盛りの姿をしていた。……そうして、あたりを見渡すと、この鋏と、いくつかの花器があった。鋏は、錆一つない銀色をしていた」
ひとつひとつ、自分が見てきたものをなぞるように、言葉にしていく。
「わたしが思うに、あれは、朽ちたものが……過日を懐かしんでいる、世界だった」
花鋏は持ち主に丁寧に磨かれ、毎日のように使われていた日を懐かしんでいた。花器は花を生けられていた頃を懐かしみ、花は己が最も美しかった日を懐かしむ。そのどれもが、現実ではすでに朽ちて、「終わった」者たちだった。
「……すべてが完璧に美しい姿で、どんな花でも……見たこともないような花でさえ、手を伸ばせば届く場所にあって。できることなら、また」
「……そんなに、幽霊花がよかったの」
ほう、と夢見るような瞳で死者の記憶の世界を語る露青に、青海がついに口を挟んだ。露青は困ったように眉を下げると、かすかに笑った。
「本当に一点の瑕疵もない、盛りの花ばかりだったからな。どんな季節の花も咲いていて、全部が月を透かしたように、淡く光って」
「季節外れの花も、伝手を辿れば見つかるものですわ」
「姉上は、一度それをやっておられるのだったな」
露青は優しく花鋏を撫でて、絹布の上に戻す。
「姉上。大丈夫だ、わたしは生きている」
「死にかけておいて、なにを悠長な」
「言っただろう、姉上が呼んでくれたから戻ってこれたのだと。わたしがあちらで最後に見たのは、姉上と同じ色の朝顔だった。それだけは、他と違ってうすぼんやりとした光をまとってはいなかったんだ」
露青は姉の髪に咲く朝顔を見て、眩し気に目を細めた。青海がはっとしたように、自分の朝顔へ手を添える。
「またいつか、あの花々を生けたいと思うのは本当だ。……だが、わたしは生きているから。枯れ朽ちるまでは、生きた花を生けるのが道理だろう」
ゆっくりと、露青の顔には笑みが浮かぶ。さやさやと、部屋の中には昼前の柔らかな風が吹き込んできた。
「幽霊花の光は、それは美しいものだったが。今の私には、今を生きて咲く花の、命が光る強さが愛おしい」
青海はしばらく黙って露青の目をじっと見つめていたが、深々としたため息とともに、がっくりと畳に手をついた。
「……本当に、世話の焼ける弟だこと」
「すまないな」
「それで、その鋏はどうなさいますの? 錆びたまま部屋にしまっておくのでは、蔵にあるのと変わらないでしょう」
「ああ。刃も欠けているから、使えるようにはならないだろうが……磨いて部屋に飾っておこうと思う」
箱に収めた鋏をいつくしむように眺めて、露青はバツが悪そうに姉に目をやった。
「あちらで、な。当主を迎えに来させるわけにもいくまい、と助力を求めたら、姉上の朝顔のところまで導いてくれたのだ、この鋏は」
いずれかの代の、この家の華道家が使った鋏なのだ。先祖に仕えたものであるなら、きっと今後も露青を助けてくれるものだろう、と彼は語った。
「生け花にとりつかれたわたしを、正気に戻してくれるかもしれない」
「その性分、本当に直してもらわないと困りますわよ。ひとまず今日からしばらくは、花にも鋏にも触れずに休んでもらいますからね」
「そ、そんな」
花を生けるしか能がないのに、と当惑した露青をじっとり据わった目で見やり、青海はすっと立ち上がる。
「どうせ錆を落として磨くのなら、餅は餅屋、研ぎは研ぎ師ですわ。いつもお世話になっているところに連絡して、訳を話してごらんなさい。それから、あの蔵も」
つらつら、と青海は今後の用事を露青に言いつけていく。
「わたくしたちの管理が行き届かずに、ご先祖が遺してくれたものを傷ませてしまったのは、とてもよろしくないことですわね?」
露青は姉を見上げ、それからいくつか瞬きをして、くすくすと笑った。
「わかった、蔵の整理と掃除、出てきた物の手入れも引き受けよう」
「よろしい。……くれぐれも、無理をしないように」
昼食はなにがよろしいかしら、と言いながら部屋を去っていく青海に、露青はようやく彼女の懸念を晴らせたと悟る。
「……ありがとう、姉上」
静かになった部屋に、床の間で揺れた花だけが、露青の声を聴いていた。